「畑のお肉」と呼ばれるほど、タンパク質と脂質が豊富な大豆。日本では昔から肉・魚のかわりに大豆を食べるなど、大豆は親しみのある食材です。この記事では、大豆の栄養と健康効果について解説します。大豆を食事にバランスよく取り入れて、頑丈な体づくりを目指しましょう。
大豆には5大栄養素が含まれている

5大栄養素とは、食べ物に含まれる栄養素のうち、人が健康に生活するために必要な栄養素のことです。筋肉や血液を作る「たんぱく質」、エネルギーのもととなる「炭水化物(糖質)」と「脂質」を三大栄養素と呼び、これに身体の働きを正常に保つ「ビタミン」と「ミネラル」を加えて5大栄養素と呼びます。大豆にはこれら栄養素がすべて含まれており、「畑の肉」と言われるのはこのためです。
【大豆(国産黄大豆)100gあたりの栄養成分】
| エネルギー | 372kcal |
| 水分 | 12.4g |
| たんぱく質 | 33.8g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 29.5g |
| 灰分 | 4.7g |
大豆は豆類の中でもたんぱく質が豊富。大豆に含まれるたんぱく質には、コレステロールを減らす、脂質の代謝を促進する、脂肪を燃焼させやすくする働きがあります。肉や魚、卵などの「動物性たんぱく質」に比べても効能は劣らず、場合によってはそれを上回るとも言われています。
大豆の脂質には、体内では作ることができないため食事からとる必要がある、不飽和脂肪酸「リノール酸」「αーリノレン酸」が多く含まれています。不飽和脂肪酸は血中のコレステロールを下げる、血圧を下げる、動脈硬化や血栓の予防などさまざまな作用があります。
炭水化物は、糖質と食物繊維の2種類があります。糖質は、身体を動かすエネルギーになったり、細胞膜を作る成分になったりします。脳にとっても糖質は欠かせない成分で、ブドウ糖不足で血糖値が下がると脳の機能が低下してしまいます。食物繊維は、便通をよくしたり、腸内環境を整える働きがあります。
大豆に多く含まれているビタミンは、下記の5種類のビタミンが多く含まれています。
ビタミンB1:糖質の代謝に不可欠なビタミン。
ビタミンB2:脂質の代謝に不可欠なビタミン。皮膚や粘膜の健康維持に関わる。
ビタミンC:皮膚や身体を構成するコラーゲンの合成に必須。
ビタミンE:強い抗酸化作用を持ち、老化防止、生活習慣病予防の効果がある。
葉酸:赤血球の生産を助ける、たんぱく質や細胞新生に必要な核酸のDNAやRNAを合成し、細胞の生産・再生する働きがある。
ミネラルは、私たちの体を作り、体のさまざまな機能の調節に欠かせないもの。大豆には、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛が含まれています。
大豆の機能性成分
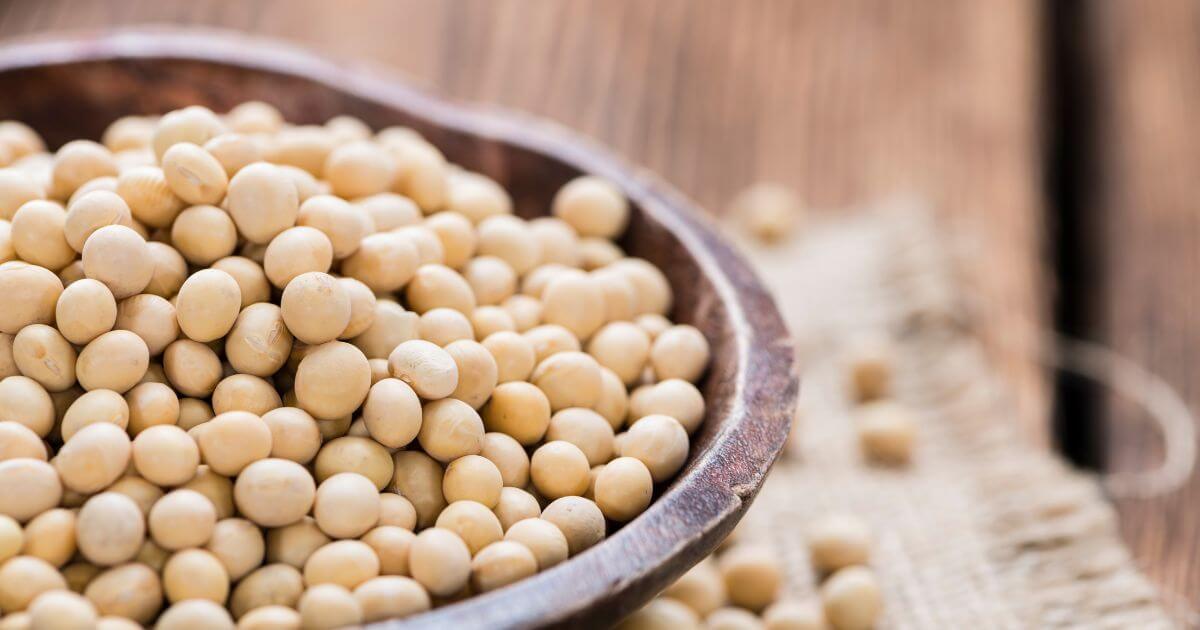
大豆には5大栄養素以外にも、私たちの健康を維持するために助けてくれる有効成分が複数含まれています。
イソフラボン
イソフラボンと女性ホルモン「エストロゲン」は分子構造が似ていて、イソフラボンは「エストロゲン」と似たような働きをしてくれます。エストロゲンは肌を美しくしたり、女性らしさを作るのに欠かせない女性ホルモン。更年期にイソフラボンを摂取すると、減少したエストロゲンを補う働きをしてくれて、更年期障害が緩和されます。また、骨密度を維持して骨粗鬆症を防いでくれる効果もあります。
レシチン
レシチンを摂取すると、体内で神経伝達物質「アセチルコリン」になります。アセチルコリンは、神経系を正常に働かせて、脳機能を改善する働きがあります。具体的には、認知症の予防、脳梗塞・脳出血の予防、ストレス予防、疲労回復、理解力・記憶力・集中力の増進など、嬉しい効果がたくさんあります。また、コレステロールを溶かして、血管の内側をきれいにする効能、肝臓の脂質の正常代謝を行う作用があります。
サポニン
血液中のコレステロールや中性脂肪を溶かすことができるため、血液を「サラサラ」に。血管内で血栓ができるのを抑えてくれます。また、脂質の生成を防ぐため、ダイエット効果が期待できます。
オリゴ等
砂糖のような甘さを持ちながら低カロリーで、ダイエットの味方。ビフィズス菌や乳酸菌などの餌になって善玉菌が増えるので、腸内環境を整えて、腸内での有害物質の発生を抑制したり、便秘の改善に役に立ちます。
このように、大豆には病気予防、ダイエットや美容対策の助けとなる栄養素が詰まっています。最近では、お肉のような食感になるよう加工された「大豆ミート」も販売されています。大豆ミートを使用したり、豆腐や納豆などの加工食品を上手に利用したりして、毎日の献立に「大豆」を上手に組み込みたいですね。
大豆は毎日食べても大丈夫?

豆腐、納豆、味噌など、日本人は大豆由来の食品を口にする機会が多いです。大豆には健康的なメリットがあるけれど、「食べ過ぎが気になる」「毎日食べても大丈夫なのか心配になる」という方もおられるかもしれませんね。
結論としては、大豆・大豆食品を毎日食べてもとくに問題はないとされています。大豆は日本人にとって昔から食べ続けてきた伝統食であり、歴史的にも大豆を食べることによって害が出てきたことはないため、神経質になる必要はありません。
大豆・大豆食品は、骨粗しょう症や更年期障害の緩和なども期待できるなど、食べるとよいことが多いです。バランスよく食事に取り入れていきましょう。
